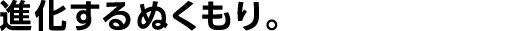相続を分かり易く解説!
手続き・税金・割合まで総まとめ

1. 相続人とは
相続人は、民法で定められた範囲の親族(配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹など)です。配偶者は常に相続人となり、血族側は「子(直系卑属)→父母・祖父母(直系尊属)→兄弟姉妹」の順に相続人となります。
2. 相続制度のしくみを知ろう
相続とは、亡くなった方(以下、被相続人とします)の財産上の権利や義務を、法律で定められた相続人が引き継ぐ制度です。
ここでいう「財産」には、預貯金・不動産・有価証券・車両・貴金属などのプラスの財産だけでなく、住宅ローン・借入金・未払い税金・連帯保証債務といったマイナスの財産も含まれます。
つまり、相続では「財産を受け取る」だけでなく、「債務も引き継ぐ」可能性がある点を理解しておくことが重要です。
相続は、被相続人の死亡によって開始します。財産を、誰がどの割合で引き継ぐかは、遺言書の有無によって大きく変わります。遺言書がある場合は、その内容が最優先されます。
一方、遺言書がない場合には、まず相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を取得するかを話し合うのが一般的です。協議がまとまらないときや目安を知りたい場合には、民法で定められた「法定相続分」を参考にして分割方法を検討します。
遺産分割協議で合意に至った場合は、遺産分割協議書を作成し、不動産登記や預貯金口座の解約等を行います。逆に協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判に移行することになります。
また、これらの相続手続きには、複数の期限が設けられています。
たとえば、相続放棄は被相続人の死亡を知ってから3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告・納付は10か月以内です。これらの期限を過ぎると、不要な税負担やトラブルにつながる恐れがあるため、早めにスケジュールを把握して準備しましょう。
相続の全体像を把握するには、「財産の範囲」「遺言書の有無」「相続人の範囲」「手続きの期限」の4つを押さえておくことが重要です。
実際の事例をご紹介するとイメージがつき易いと思いますので、次の章をご覧ください。
3. 事例紹介

ご自身で相続手続きを進めようとしていたAさんでしたが、故人である叔父の出生から死亡まで、複数の市区町村にまたがる戸籍を取得する必要があると知り、対応に困っていました。最近始まった戸籍の広域交付制度では兄弟姉妹や叔父叔母の戸籍は取得できないため、手続きは想像以上に複雑です。
そこで、司法書士に依頼したところ、必要な戸籍の特定から取得までを代行してもらうことができ、無事に相続手続きを進めることができました。
また、司法書士のアドバイスで、取得した戸籍等を提出して法定相続情報証明制度を利用。複数の金融機関の相続手続きを同時に進めるなど、スムーズに相続手続きを進めることができました。
4. 法定相続人の範囲と優先順位
本章からは、具体的事項について解説していきます。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを話し合うことが一般的です。
ただし、協議がまとまらない場合や分割割合の目安を知りたい場合には、民法で定められた法定相続分を参考にします。
ここでは、法定相続人の範囲と優先順位について整理します。
4-1. 法定相続人の順位
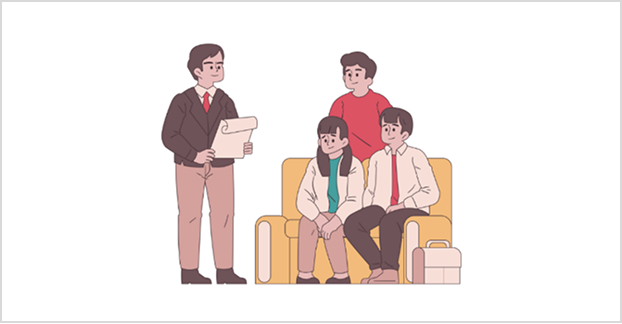
まず押さえておきたいのは、配偶者は常に相続人になるという点です。
配偶者は順位に関係なく必ず相続人となり、以下の順位のとおり、子・親・兄弟姉妹のいずれかと共同で相続します。
第1順位:子どもとその代襲相続人
子どもは最優先で法定相続人です。
もし、子どもがすでに亡くなっている場合、その子ども(孫)が相続します(代襲相続人と言います)。
第2順位:父母・祖父母
第一順位がいない場合は、両親や祖父母など(直系尊属と言います)が相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹
第一順位および第二順位がいない場合は、兄弟姉妹が相続人です。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となりますが、甥・姪が亡くなっている場合はそこで代襲が終了します。
4-2. 兄弟姉妹が相続人になる場合のポイント
前述のとおり、兄弟姉妹が法定相続人となるのは、被相続人に子ども、そして系尊属もいない場合に限られます。
兄弟姉妹が複数いる場合、相続分は原則として平等です。
ただし、兄弟姉妹のうち父母が異なる「半血兄弟姉妹」は、同父母の兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と比べて相続分が2分の1となります。
また、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子ども(甥・姪)が代襲相続人となりますが、甥・姪が亡くなっている場合には代襲相続は発生しません。
4-3. 相続順位と相続割合(法定相続分)割合一覧表
| 相続人の組合せ | 相続割合の目安(法定相続分) |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者 100% |
| 配偶者+子(第1順位) | 配偶者 1/2 ・ 子(全員で)1/2 |
| 配偶者+父母等(第2順位) | 配偶者 2/3 ・ 直系尊属(全員で)1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者 3/4 ・ 兄弟姉妹(全員で)1/4 |
同順位が複数いる場合は等分(例:子が2人なら各1/4)。上記は法定相続分の基本であり、遺産分割協議で合意すれば異なる按分も可能です。
※この表はあくまで法定相続分の目安です。相続人全員の合意による遺産分割協議で、異なる割合にすることも可能です。
5. 相続手続きの流れと期限チェックリスト
相続の手続きには、複数の期限が設けられており、期限を守らないと不要なトラブルや税負担につながることがあります。
ここでは、相続開始(被相続人の死亡)からの手続きの流れと、主な期限を整理します。
| 期限 | 手続き | 提出先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届、火葬許可申請、世帯主変更届 | 市区町村役場 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 | 法務局 |
5-1. 死亡から7日以内に済ませる届け出一覧
被相続人が亡くなった直後は、葬儀の準備と並行していくつかの手続きを行う必要があります。中でも重要なのが、死亡届をはじめとした初期手続きです。
- • 死亡届の提出:被相続人の死亡を市区町村に届け出ます。
- • 火葬許可申請:死亡届と同時に行うのが一般的です。葬儀社が手続きを代行してくれる場合もあります。
- • 世帯主変更届:世帯主が亡くなった場合に必要な手続きです。
※いずれも提出先は市区町村役場です。
5-2. 相続放棄・限定承認は3カ月以内に判断
被相続人が亡くなった場合、相続人は財産を引き継ぐかどうかを選択できます。
この判断には「相続放棄」と「限定承認」の2つがあり、いずれも被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
• 相続放棄
財産も借金も一切相続しない方法です。借金超過が予想される場合などに選択されます。
相続放棄をすると、その人は最初から「相続人ではなかった」扱いとなり、次順位の相続人に権利が移ります。
• 限定承認
遺産の範囲内で借金を返済し、残りがあれば受け取る方法です。
相続人全員の合意が必要で、手続きも比較的複雑です。
5-3. 準確定申告は4カ月以内に提出
被相続人が個人事業主の場合や、給与以外の所得が一定以上あった場合は、死亡年分の所得税を申告します。
これを準確定申告といい、相続人が連署して提出します。
- • 期限:死亡を知った日の翌日から4か月以内
- • 提出先:被相続人の住所地を管轄する税務署
5-4. 相続税申告と納付は10カ月以内
相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。
• 基礎控除額の計算式
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
• 期限
死亡を知った日の翌日から10か月以内
• 提出先
被相続人の住所地を管轄する税務署
期限を過ぎると延滞税・加算税が発生する可能性があるため、早めの準備が必要です。
6. 相続税の計算方法と節税の基本
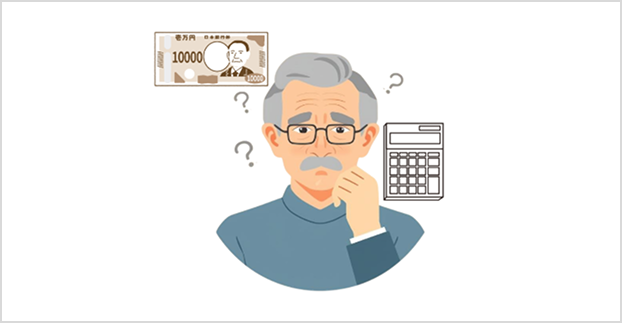
相続税の計算では、まず、相続財産の総額を計算し、そこから基礎控除額を差し引いて「課税対象額」を求めます。
次に、この課税対象額を、いったん「法律で決められた割合(法定相続分)で分けた」と仮定して、相続人各人の金額ごとに相続税率をかけて計算し、最後に合計することで、相続税の額が出てきます。
課税対象額にそのまま税率をかけるわけではないことに注意です。
相続財産の総額には、現金・預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産に加え、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」も含めます。
一方で、住宅ローンや借入金、葬儀費用などは差し引くことができます。
相続財産の総額 =(プラスの財産)+(みなし相続財産)−(債務・葬儀費用)
また、基礎控除額は次の式で算出します。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例:相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円 です。
相続財産の総額が基礎控除額を超えない場合、相続税の申告は不要です。
6-1. 税率・控除額一覧と計算例
相続税額は、課税対象額を法定相続分で分割し、下記の税率・控除額を使って計算します。
| 課税対象額(法定相続分ごと) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
計算例1:配偶者と子ども2人の場合
- • 遺産総額:6,000万円
- • 相続人:妻+子ども2人
- • 基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
- • 課税遺産総額:6,000万円−4,800万円=1,200万円
- • 法定相続分:妻1/2、子ども各1/4
- • 相続税額の計算:
妻:1,200万円×1/2=600万円 → 税率10% → 60万円
子ども:1,200万円×1/4=300万円 → 税率10% → 各30万円
- • 合計相続税額:120万円
- • 補足
配偶者には「配偶者の税額軽減」が適用され、法定相続分または1億6,000万円まで非課税。この例では、妻の相続税は最終的にゼロになる可能性が高いです。
計算例2:子ども2人のみの場合
- • 遺産総額:5,000万円
- • 相続人:子ども2人
- • 基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
- • 課税遺産総額:5,000万円−4,200万円=800万円
- • 法定相続分:子ども各1/2
- • 相続税額の計算:子ども:800万円×1/2=400万円 → 税率10% → 各40万円
- • 合計相続税額:80万円
7. 遺産の分割方法と協議の進め方
遺言書が無い場合や、記載が不十分な場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を取得するかを話し合います。
遺産分割の3つの方法
• 現物分割
財産をそのまま現物で分割する方法です。
例:長男が自宅、二男が貯金を取得
• 換価分割
不動産や有価証券などの遺産を売却し、その売却代金を分割する方法です。
不動産を複数人で共有したくない場合によく使われます。
• 代償分割
特定の相続人が遺産をまとめて取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。不動産を一人が引き継ぐケースなどで選ばれます。
7-1. 遺産分割協議書の作成手順
1. 相続人の確定
戸籍を取得し、相続人全員を確認します。抜け漏れがあると協議が無効になる可能性があるため注意が必要です。
2. 遺産の範囲を確定
預貯金、不動産、株式、保険金などの相続財産を洗い出します。住宅ローンや借金などマイナスの財産も対象です。
3. 遺産分割協議と協議書の作成
誰がどの財産を相続するかを協議します。協議内容がまとまったら、相続人全員が署名・押印した「遺産分割協議書」を作成します。
この協議書は、相続登記をする際に必要になります。また、預貯金口座の解約などで提出を求められることが多いため、作成しておくと安心でしょう。
7-2. 調停・審判になったときの対応
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。
調停は、裁判所が選任する調停委員を介して相続人同士が話し合い、合意を目指す手続きです。
中立的な立場から助言を受けられるため、相続人同士で直接交渉するよりも冷静に話し合えるメリットがあります。
また、調停でも合意に至らない場合は、家庭裁判所が分割方法を決定する「審判」に移行します。
審判では、裁判所が法定相続分や事情を考慮し、遺産分割の内容を最終的に決定します。審判結果には法的拘束力があるため、相続人はこれに従う必要があります。
調停や審判は、時間や費用の負担が大きくなる可能性があるため、可能であれば相続人間での協議で解決を目指すのが望ましいといえます。
8. FAQ:よくある質問と相談先
相続税がかかるのはどんなときですか?
相続税は、相続財産の総額が 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数) を超える場合に発生します。
基礎控除額以内であれば、相続税の申告・納付は不要です。
相続放棄は一部の財産だけ放棄できますか?
できません。相続放棄は「すべての相続財産を放棄する」手続きであり、一部だけの放棄はできません。
特定の財産を受け取らない形にしたい場合は、遺産分割協議で他の相続人と話し合う必要があります。
相続税の申告期限を過ぎたらどうなりますか?
申告期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性があります。
早めに税理士や税務署に相談し、申告手続きを進めることが重要です。
専門家にはどこに相談すればいいですか?
相続に関する相談は、内容に応じて以下の専門家が適任です。
• 司法書士:不動産登記、預貯金口座の解約、遺産分割協議書の作成など
• 行政書士:車の名義変更、戸籍謄本の収集など
• 税理士:相続税の申告など
• 弁護士:相続人間のトラブル、遺産分割調停や審判など
• 市区町村の無料相談窓口:各自治体での相談会も活用可能
【まとめ】相続手続きでお困りの場合は
弊社NCPグループは累計で30万件以上の相続相談を承っています。
ライフエンディング分野で国内トップクラスの実績を誇り、終活支援サービスである「日本郵便の終活日和」と提携しています。
初回のご相談は無料で承りますので、具体的な行動を相続前、相続発生時に知りたい方は以下の電話番号またはWebからお問い合わせください。
この記事の執筆者

株式会社NCP相続センター
「NCP」とはNew(新しい)Consulting(相談できる)Partner(協力者)の略です。ライフエンディング分野で国内トップクラスの実績を誇り、増加し続ける相続手続・遺言作成等をサポートしています。グループ本部は東京都新宿区四谷に所在していますが、北は札幌~南は福岡まで、全国各地に50カ所を超える拠点があり、お客様にご相談いただきやすい環境を整備しております。